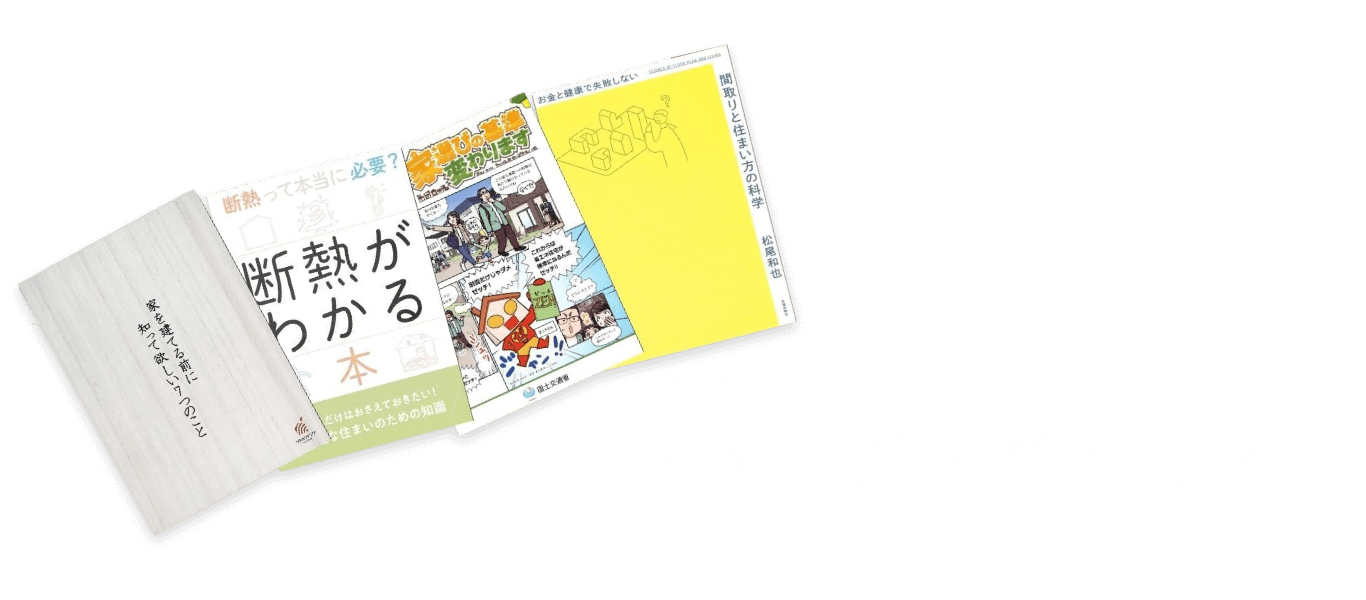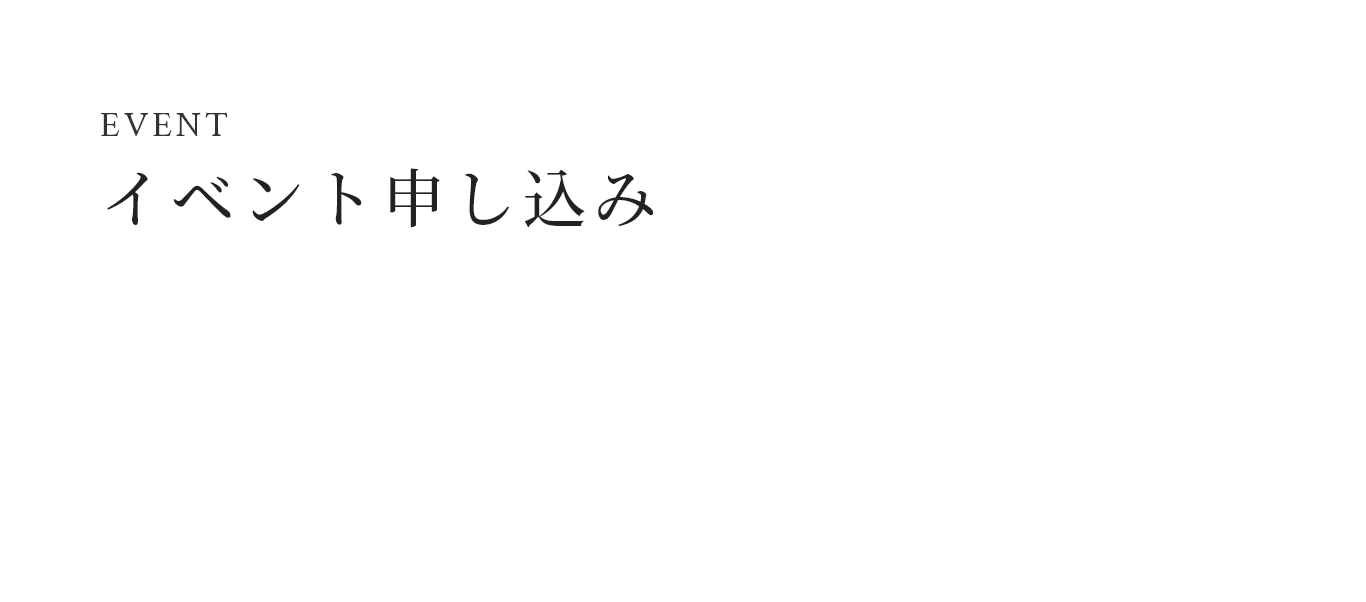2025.04.10
長期優良住宅って?メリットデメリットを解説!

こんにちは。
家づくりプランナーの花田です。
本日は、「長期優良住宅」について解説します!
目次
長期優良住宅とは?
長期にわたり、良好な状態で使用するための措置を講じられた優良な住宅のことを言います。
環境に優しく、耐震性や省エネルギー性などが高い住宅として認定されるため、さまざまなメリットがあります。

長期優良住宅の認定基準
長期優良住宅の認定を受けるには、以下の基準を満たす必要があります。
①劣化対策
少なくとも、75年~100年程度の耐久性を確保できること。
柱や梁などの構造躯体が少なくとも75年~95年程度(3世代)継続して使用できる措置に加えて、例えば、木造住宅であれば、床下や小屋裏に点検口を設置し、床下空間に330mm以上の高さを確保するなどの追加措置が必要になります。
②耐震性
建築基準法の1.25倍以上の耐震性(耐震等級2)を持つこと。
建築基準法で想定している大地震がおきても、少しの改修で住み続けられるよう、損傷の軽減を図るため、例えば、住宅性能表示制度の耐震等級(倒壊等防止)の1~3等級の等級2などが必要になります。
ただし、壁量計算による場合は耐震等級3が必要です。
その他にも耐震等級1かつ、安全限界時の層間変形が1/100(木造は1/40)以下や品確法が定める免震建築物なども対象になります。

③省エネルギー性
必要な断熱性能などの省エネ性能が確保されていること。
断熱等性能等級5、かつ一次エネルギー消費量等級6を満たす必要があります。
暖冷房時の省エネ化をはかるため屋根、床、壁、天井、開口部の断熱性能を高くします。

④維持管理・更新の容易性
構造区体が100年程度継続使用できたとしても、給排水管などはその間に取替や補修が必要になるため、点検・補修がしやすいことがもとめられています。
原則、住宅性能表示制度の維持管理対策等級の最高等級3の性能が必要です。
⑤可変性
暮らす人のライフスタイルに合わせて、間取りを変更できるように準備しておくこと。
共同住宅にのみ適用される基準で、天井の高さ2,650mm以上必要になります。
⑥バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できること。
住宅性能表示制度の高齢者対策等級の1~5等級の等級3に相当しますが、共同住宅のみ適用される基準ですので、一般の住宅には該当しません。
⑦居住環境
良好な住環境の形成に配慮された設計であり、住宅の建つ地域で決められた景観などのルールに則って街並みに調和することが求められています。

⑧住戸面積
良好な居住水準を確保するための住戸の面積を定めています。
戸建ては75㎡以上、共同住宅は45㎡以上となっています。
また、一つの階の床面積が階段を含めずに、40㎡以上必要です。
⑨維持保全計画
建築後の定期的な点検・補修などの計画を行うことが求められています。
「構造体力上主要な部分」「雨水の侵入を防止する部分」「給水・排水の設備」について維持保全計画を作成して点検の時期・内容を定める必要があります。
⑩災害配慮
自然災害が起きたときに、被害を防止もしくは、軽減できる措置が必要になります。
災害発生のリスクを、所轄行政庁がハザードマップで示しています。
災害発生リスクがある地域に長期優良住宅を建築する場合は、リスクに応じて所轄行政庁が定める措置が必要になります。
長期優良住宅認定までの流れ
①事前準備
長期優良住宅の基準に沿って設計を進めます。
②書類作成・申請
「長期優良住宅 建築等計画認定申請書」を作成をします。
各種図面、性能証明書、維持保全計画書などを添付して第三者の審査機関で一次審査後に地元の行政に提出します。
もしくは、地元の行政に一括で提出もできますが、弊社の建築エリアですと第三者機関の評価書はないですかと言われますので、第三者機関で評価をしてもらってからの方が審査が早くなります。

③審査・認定
申請後、書類と設計内容を審査。
問題なければ「認定通知書」が発行されます。
④着工
認定後に着工。
認定前に着工すると対象外になるため注意が必要です。
⑤完了審査・報告
建築後、申請内容通りに施工されたかをチェックします。
完了報告書を提出して認定完了です。

長期優良住宅のメリット・デメリット
メリット
・耐久性
しっかりとした構造や耐震性、省エネ性能などが求められるため、長期的に使い続けられるよう設計されており、耐久性が高いです。
・資産価値
長期優良住宅に認定されると、品質が高く、性能が維持されるため、売却時に価値が高くなる可能性があります。
・補助金、税の優遇
長期優良住宅に認定されると、補助金や税制の優遇が受けられる場合があります。
登録免許税(登記する際法務局に支払うお金) 0.15%→0.1%
固定資産税 1/2減額期間が3年→5年に
不動産取得税 控除1200万円→1300万円に
・住宅ローン控除の上限額UP

デメリット
・コストがかかる
長期優良住宅の性能基準を満たすための施工が必要なので、通常よりもコストがかかる場合があります。
・申請や認定に手間と時間がかかる
設計、書類作成、審査などと通常よりも手間がかかり、認定まで時間を要する場合があります。
・定期的な点検、修繕の義務
認定を受けた後は、点検・修繕などを定期的に実施する義務があります。
これらを怠ると認定が取り消しされる場合もありますので注意が必要です。

長期優良住宅はどんな人におすすめ?
1.長く安心して住み続けたい人
耐久性、耐震性など性能が高いため、長く安心して暮らしたい方。
2.家を資産として考えたい人
長期優良住宅として認定されると資産価値が下がりにくく、将来的売却などの場合に有利になります。
3.税制優遇などの制度を活用したい人
住宅ローン控除や固定資産税の減税を利用したい人にメリットとなります。
4.家を大切にしたい人
住宅が大好き、住宅を大切にしたい、そんな方には維持保全計画があるので、その通りに維持保全を行うことで長く愛着を持って暮らせます。

長期優良住宅認定取得には、メリットもあればデメリットもあります。
そのため、長期優良住宅を選ぶ際は、費用や維持管理の手間、工期などを考慮することが重要です。
また、基準をしっかり満たせるよう工務店・ハウスメーカー選びも重要です。
失敗・後悔しない住宅を建てるならワダハウジングへぜひご相談ください。
ご相談お待ちしております。

ワダハウジング和田製材株式会社
花田結香