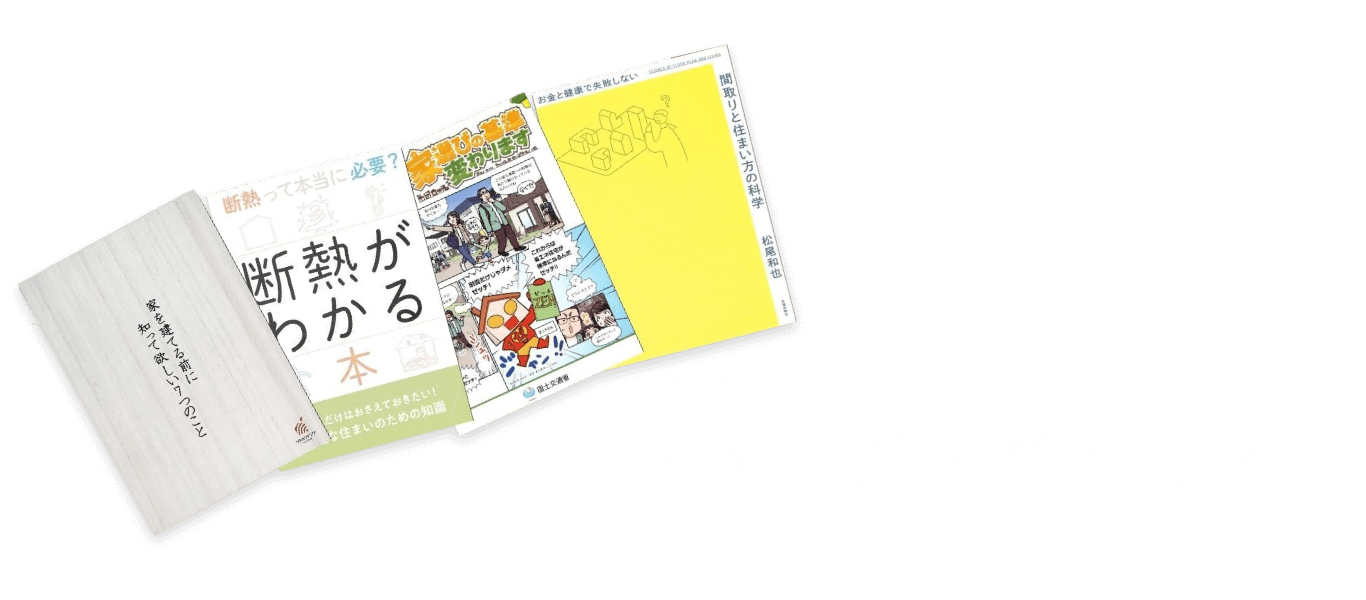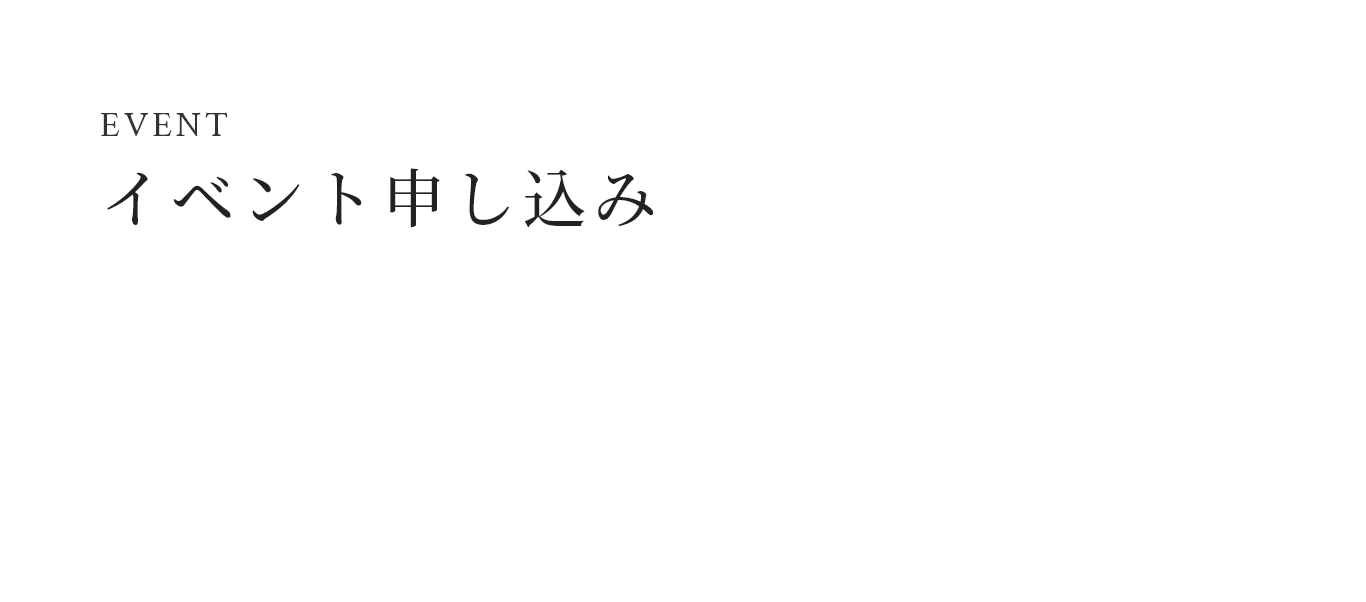2025.04.07
土岐市の工務店が新築住宅の丈夫な基礎作りを紹介!

工事現場の管理やメンテナンス等を担当する工務課。
植松達矢です。
注文住宅の工事についての事を色々紹介しています。
・二級施工管理技士。
・福祉住環境コーディネーター2級。
新築住宅の基礎工事では初めに、丁張(住宅の位置出し)から作業を行っていきます。
新築住宅の基礎を造る位置のまわりに杭を打ち、高さを合わせて抜き材(長い木の板)を外周に設置。
抜き材に基礎の通りに合わせた印を付けて釘を打ち、水糸を通して基礎の位置を出します。

水糸の高さを基準に床掘(土のスキ取り)を行い、基礎の底の高さになる様に砕石を敷き転圧を行い、基礎をのせる床を作成。
完了後は地中からの湿気を止めるフィルムを敷き詰め、外周をコンクリートで押さえる様に流しコテで高さ調整を行い、固まると捨コン打設の完了になります。

完了後は工務店の図面に合わせて新築住宅の基礎の位置出しを行い、配筋の工事に備えて行きます。

配筋工事が始まるとたくさんの鉄筋を搬入して、住宅を支える丈夫な基礎の骨組み作りの準備。
配筋では工務店の図面で決められた位置に合わせて、鉄筋を配置して強度が出る様に組み立てて行きます。

この時に鉄筋を細い番線(なまし鉄で出来た柔らかい針金)で繋ぎ合わせて基礎の打設前に仮組み。

組み立てが終わると配筋検査。
JIO(日本住宅保証検査機構)工務店とは別の検査機関の元に送った、基礎図面の通りに鉄筋が配置されているかの検査を行います。

鉄筋の繋ぎ手の位置・立ち上がりの鉄筋の通りや間隔・型枠や地面との隙間(コンクリートの厚み)等を確認して、合格しなければ住宅基礎のコンクリート打設には進めません。
無事に検査に合格するとコンクリートの打設(住宅基礎の肉付け工事)を行って行きます。

住宅基礎のコンクリートの打設は工務店の工事方法によりますが、おもに2回に分かれます。
ベース(床下になる部分)の打設。
立ち上がり(住宅の土台を支える部分)の打設に分けて行います。
ベースの打設では運び込まれた大量のコンクリートを型枠の中に、ポンプ車が調整しながら流し込みます。
まずは基礎外周の低い所からコンクリートの打設開始です。

外周を打ち終わると、コンクリートが硬くなる前に住宅の奥の位置から床部分を流し込んで行きます。
この時に棒状の振動する機械や大きなトンボ(T字型の道具)を使い、コンクリートを広げたり振動を与えたりして、隙間なく型枠を満たし丈夫で密実な基礎を作って行きます。

ベースの打設完了後は基礎を固める為に養生期間。
乾燥が進むと型枠の組み替えを行い、住宅の土台と基礎を繋ぎとめる為にボルトを設置。

ボルトの設置後に工務店の検査を行い基礎図面と位置が合っているかを確認。
位置の調整等を行い、合格なら次の立ち上がり打設に工事を進めていきます。
立ち上がり打設の工事では型枠に、住宅の土台の高さから1cm下に合わせ、目印の磁石を付けて打設準備完了。

目印に合わせてコンクリートを流し込み、機械で適度に振動を与えて隙間なく型枠を満たす事で、丈夫で密実な基礎を作って行きます。
予定の高さになった所で基礎の表面をなでて細かい凹凸を付け、仕上げ材の付きが良くなる様に加工。

全ての打設が完了し少し硬化させた後で、レベラー(表面を平らに仕上げる滑らかな材料)を流し込み基礎の高さ(レベル)をそろえて行きます。

完了後は4~5日程養生期間を置いて基礎を硬化させます。
型枠を外し基礎の高さを整えて、大まかな工事が完了です。

型枠を外した後は基礎の周りの土を埋め戻し、玄関の下地等を作り基礎工事が全て完了。
その後は基礎内(床下)の配管や土台の設置等を行い。
上棟(住宅を組み上げる工事)の準備を進めて行きます。
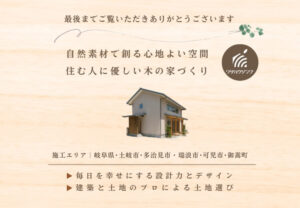

土岐市の工務店で新築住宅の丈夫な基礎作りをする
ワダハウジング和田製材株式会社
・二級施工管理技士
・福祉住環境コーディネーター2級
植松達矢

初投稿 2022.11.24
2022.12.10
改修 2025.04.07